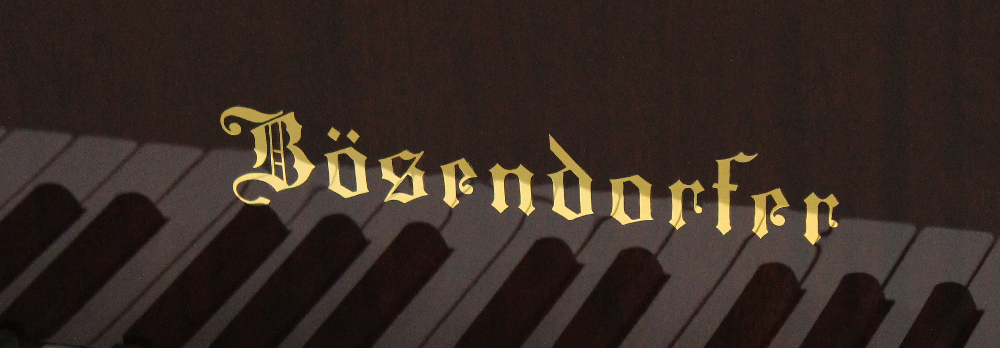
Bösendorfer(ベーゼンドルファー)
キャッチフレーズ
創業190年を誇る"音楽の都"ウィーンの名器
創業者
イグナーツ・ベーゼンドルファー
創業年
1828(文政11)年
本社所在地・製造拠点
ウィーン(オーストリア)
ウィーナー・ノイシュタット工場(オーストリア)
特徴
「ウィンナートーン」といわれる、オーケストラ・サウンドを思わせる多彩な音色

スタインウェイの強靭で煌びやか、パーカッション的な響きに対し、ベーゼンドルファーは打鍵した後の持続音が長く、また柔らかくて多彩、暖かい音色が特徴で、クラシックのみならずジャズ、ポップスなど幅広いジャンルに対応しています。
「至福のピアニッシモ」といわれる、ピアノ全体が共鳴する木材の柔らかく美しい響き

ベーゼンドルファーで使用される木材の85%以上が響板でも使用されるスプルースであり、海抜1000メートルの中央アルプスのある特定の地域で育った楽器に最適なスプルースのみを使用し、最長で6年間の天然乾燥を経て使用されます。各パーツが十分に時間をかけて最良の状態で使用されるため、演奏者自身に理想の共鳴が得られるよう設計・製造されています。
「総一本張り」張弦方式による純粋で安定感のあるサウンド

ベーゼンドルファーの全ての弦は、一本一本が独立して張られます。これによってより良い調律安定性が得られ、より不純な音がなくなり純粋な響き、音階を得ることが保証されます。また、中音域で演奏中に弦が一本切れたとしても、3本のうち1本だけが影響を受けてあとの2本が残るため、演奏は中断せずそのまま続けることができ、音の損失は最小限となります。
主要モデル
【アップライトピアノ】
Model130CL、Model120CL
【グランドピアノ】
Model290 Imperial、Model280VC、Model225、Model214VC、Model200、Model185、Model170、Model155
歴史(略歴)
19歳よりオルガン製作を学んたウィーン生まれの職人、イグナッツ・ベーゼンドルファーにより、ベートーヴェン、シューベルト、リストなど偉大な作曲家を生み出したウィーンで、1828年、ベーゼンドルファー社が設立されました。
2年後の1830年にフランツ・リストと出会います。その激しい演奏のために当時製造されていたどのピアノもリサイタルの演奏に耐えられなかったのですが、ベーゼンドルファーのピアノがリストの演奏に耐え抜き演奏会が成功を収めたことを機に、美しい音色と共にベーゼンドルファーの名は広く知れ渡る事となりました。
1939年にはオーストリア皇帝から実績が認められ、「宮廷及び会議所ご用達のピアノ製造者」の称号を授けられる名誉を与えられました。
その後、演奏会場の大型化やオーケストラの大規模化に対応するため、ベーゼンドルファーも他のピアノメーカーと同様に音量の増大と楽器の強度を上げる事に取り組んでいきましたが、一方では人の心を惹きつける「至福のピアニッシモ」を磨き続け、商業ベースに流されずない丁寧な手作業による製造を維持し続けました。
第二次世界大戦後は経営がアメリカの企業に移りましたが、2002年にオーストリアの銀行グループが経営権を取得しオーストリアのピアノメーカーとして復帰した後、2007年にはヤマハ(日本)の子会社となっています。
名作
主要演奏者
| アーティスト名 |
|---|
| フランツ・リスト(ハンガリー) |
| シフ・アンドラーシュ(ハンガリー) |
| スヴャトスラフ・リヒテル(ウクライナ) |
| ヨハン・シュトラウス(オーストリア) |
| パウル・バドゥラ=スコダ(オーストリア) |
| イェルク・デムス(オーストリア) |
| ヨハネス・ブラームス(ドイツ) |
| ヴィルヘルム・バックハウス(ドイツ) |
| フェルッチョ・ブゾーニ(イタリア) |
| レナード・バーンスタイン(アメリカ) |
| オスカー・エマニュエル・ピーターソン(カナダ) |









